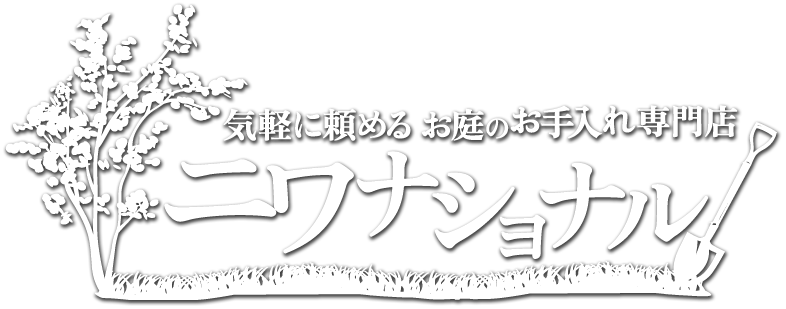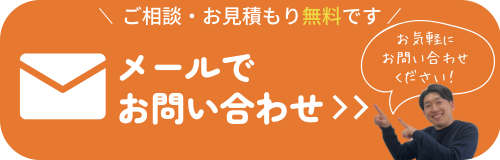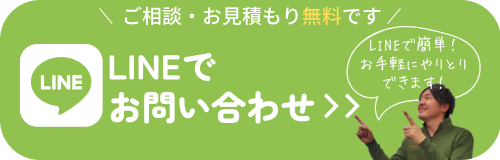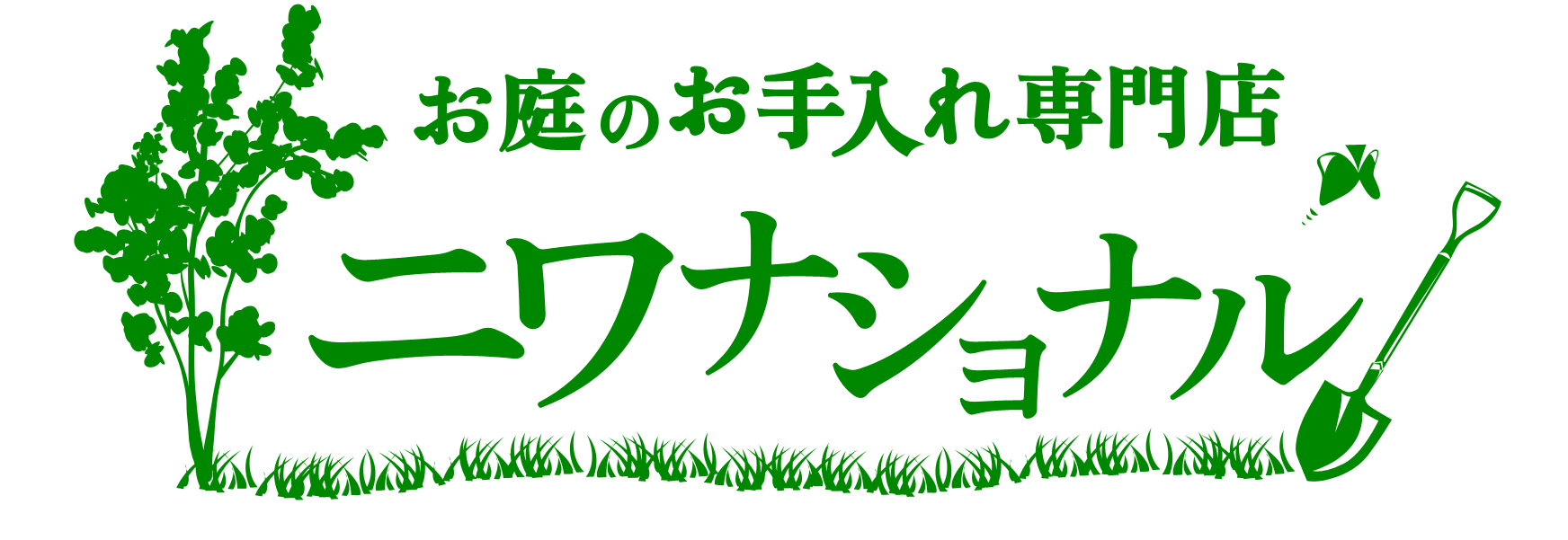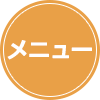公開日
立冬を過ぎ、急に寒くなってきましたね。庭では、冬を迎えるための準備が始まります。中でも「雪囲い」は、日本海側や豪雪地帯の伝統的な風物詩で、雪の重みから樹木や建物を守るため、雪国の人々が受け継いできた美しい知恵です。
海外でも植物の冬支度は一般的ですが、日本のような「雪囲い」はほとんど見られません。今回は、日本独自の雪囲いの文化と、海外の冬支度の違いについて紹介します。
日本の雪囲い:冬の風物詩
雪囲いは、雪の重みで枝が折れたり、建物が損傷しないように、竹や縄、茅(かや)などで支えや囲いを設ける伝統的な方法です。特に有名なのは、金沢の兼六園や岐阜県白川村の合掌造りです。

兼六園では、毎年11月から12月中旬にかけて「雪吊り」の作業が始まります。庭師や造園業者が松の木に支柱を立て、縄を円錐状に張って雪の重みから守ります。この風景は、北国ならではの美しいアートとして、多くの観光客を惹きつけています。

一方、岐阜県白川村の合掌造りでは、屋根から落ちる雪の重みから建物を守るため、木製板や茅で「おだれ」と呼ばれる囲いを設置します。これは、世界遺産の景観を守るため、地域の伝統や美しさを大切にしながら行われています。
雪国では、庭の植物だけでなく、家屋自体も雪から守る雪囲いが必要なんですね。
海外の冬支度との違い
海外では、植物の冬支度も大切ですが、日本のような雪囲いはほとんどありません。
日本では湿った重い雪が多く、枝や建物に大きな負担をかけるため、雪囲いの文化が発達しました。一方で欧米の雪は軽く乾いており、積雪による被害が少ないため、囲いの必要があまりないのです。
ヨーロッパや北米では、主にマルチング(落ち葉やバークチップ、わらなどで根元を覆う)、不織布やフリースで植物を包む、温室やポリトンネルの利用など、現地の気候に合った方法が主流です。

特に北米の一部地域では、雪そのものが断熱材として機能するため、特別な雪囲いをしなくても、自然の雪が植物を守ってくれます。一方、雪のない地域では、乾燥や霜から守るため、カバーやマルチが重視されます。
自宅の庭にも取り入れたい「雪囲い」
雪国では昔から、家屋や庭木を守るために雪囲いを施すのが冬の恒例行事でした。けれど最近では、雪の少ない地域でも、この伝統的な風景を“冬のアート”として楽しむ人が増えています。

竹や縄、藁などの自然素材を使った雪囲いは、実用的であると同時に見た目も美しく、庭に温もりと風情を添えてくれます。雪囲いの方法を紹介するSNS動画も人気で、DIYで自分流の囲いを楽しむ人も多く、日本の冬文化が新しい形で息づいています。
冬のもうひとつの知恵「こも巻き」

冬の庭を守る日本の伝統技法に「こも巻き」があります。
藁でできた筵(むしろ)を木の幹に巻きつける作業で、一見すると防寒対策のように思われますが、実は害虫対策が主な目的です。
冬の間、カイガラムシやマツカレハなどの害虫は、幹の根元で越冬します。そこで、こも巻きを幹の下部に施すことで、虫たちがその中に入り込み、春先にこもを外すと同時に一緒に焼却するのです。まさに、自然と共に生きる昔ながらの知恵ですね。
現代では、薬剤を使わないエコな害虫対策として再注目されています。雪の少ない地域でも、松や梅などを育てている人なら、こも巻きはぜひ試してみたい方法です。藁の質感や見た目も美しく、冬の庭に温もりを添えてくれます。
まとめ
冬の静けさの中に、縄や藁の温もりが映える庭は、日本の冬の美しさを実感します。自然と共にある暮らしの知恵は、どんな地域に暮らしていても心を豊かにしてくれるものですね。
日本独自の雪囲いは、自然と共生する知恵と美しさが融合した冬の風物詩です。今年の冬は、雪囲いの風景を楽しみながら、庭や庭園の冬支度を進めてみてはいかがでしょうか。