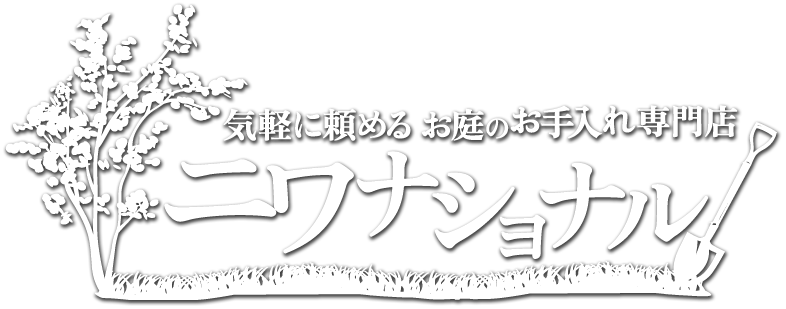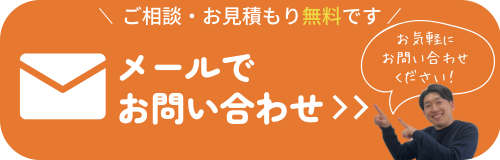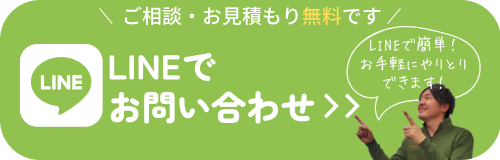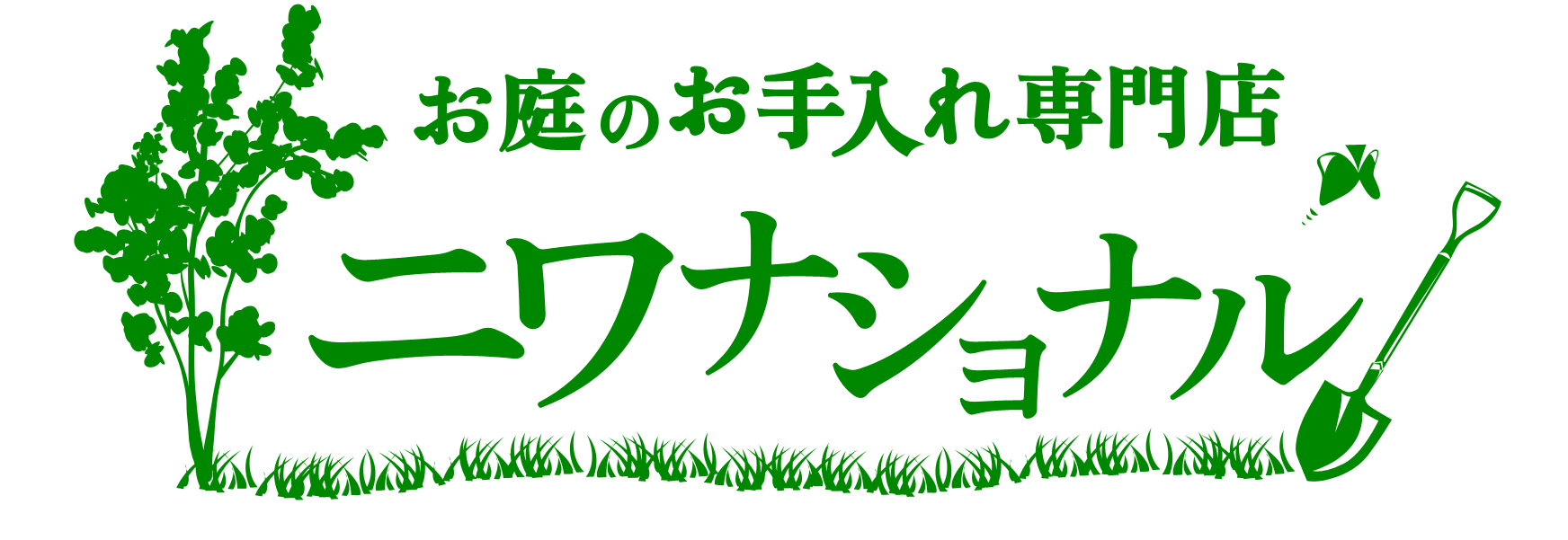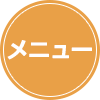公開日 2025/08/15
更新日

お庭や公園、街路樹でよく見かけるアカマツやクロマツ🌲。
そんな松の葉をじわじわと黄変させてしまうのが、マツカキカイガラムシ(マツにつくカイガラムシ)です🐚。
体は小さいですが、葉や葉鞘に寄生して汁を吸い、時間をかけて樹勢を弱らせます。
この記事では、マツにつくカイガラムシの発生時期・被害の特徴・効果的な予防法を解説します。
大切な松を守るためのチェックポイント、ぜひ参考にしてください🌿。
マツカイガラムシとは?
マツにつくカイガラムシは、アカマツやクロマツの葉や葉鞘に寄生して汁を吸う害虫です。
代表的な種類にマツカキカイガラムシがあり、樹勢をじわじわと弱らせ、景観も損なってしまいます💦。
特に葉の一部が黄変(黄色く変色)するのが特徴で、放置すると広範囲に被害が拡大します。
🍂発生時期とライフサイクル
- 幼虫の発生時期:年2回(5〜6月、8〜9月)
- 成虫の特徴:硬い介殻(カイガラのような殻)をまとっており、殺虫剤が効きにくい
- 被害の進み方:幼虫・成虫ともに吸汁し、葉の色を変えてしまう
🛡防除のポイント
-
幼虫期を狙った殺虫剤散布
幼虫は介殻を持たないため、薬剤が効きやすく、防除効果が高まります💨。 -
成虫への薬剤散布は効きにくい
成虫は介殻で覆われているため、物理的な除去(ブラシや水流)も有効です。 -
早期発見と定期的な点検
発生時期を把握して観察することで、被害の広がりを防げます🔍。
🌿まとめ|「時期」と「初期対応」がカギ
マツカイガラムシは小さいながらも、長く寄生することで松の健康をじわじわと奪います。
5〜6月・8〜9月の幼虫発生期に集中防除することが、被害を最小限に抑えるポイントです。
ニワナショナルでは、松の害虫診断や幼虫期の防除作業にも対応しています。
「葉が黄変してきた…」と感じたら、早めにご相談ください📞😊